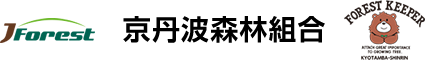「京都の林業魅力丸ごと体験」を実施しました。
京都府主催「京都の林業魅力丸ごと体験」が、7/23~7/27に行われました。
本取り組みは京都府立林業大学校の体験入学として林業の授業や地域の魅力について体験し、林業や京丹波地域を知っていただくきっかけ作りを目的としています。
当組合では林業体験としまして測量や枝打ち、チェーンソー体験、林業現場の見学・体験を実施しました。
当日の様子についていくつかご紹介します。
測量体験
林業では従来ではコンパスと測量ロープを使用したアナログな手法で森林の測量を行っていました。
この方法では野帳への記入、ロープの引っ張りなど時間と手間がかかりました。
現代ではこの記入や測定を電子的に行うデジタルコンパスが普及し、簡単に図化することができるようになりました。
さらに近年ではGPSを用いた測量もできるようになり、更なる省力化が進んでいます。
それらの器具についての進化や特徴について参加者の皆さんに体験していただき、林業の基礎となる測量の大切さについて学んでいただきました。
 コンパス測量の様子
コンパス測量の様子
枝打ち体験
続いて、節の少ない質の高い材を作るための施業である枝打ちを体験してもらいました。
節の少ない木は見た目の美しさだけでなく、木材価格に何倍もの差がつきます。
さらに林床に光が入るようになることで、下草を増やし健全な森林空間を作ることにも役立ちます。
質の高い木・健全な森作りについて学んでいただくと同時に、真夏の作業の大変さについても少し体験していただきました。
 枝打ちの様子
枝打ちの様子
チェーンソー体験
林業の代表的機械であるチェーンソーについて、丸太切り体験をしていただきました。
近年はチェーンソー作業に関する安全装備品も充実し、万が一の時にもリスクを低減する仕組み作りが進んでいます。
ほとんどの方が初めて触ることになりましたので、丁寧に指導しながら安全な取り扱いを心掛けてチャレンジしていただきました。
 丸太切りの様子
丸太切りの様子
林業現場見学
当組合で行っている間伐の様子について見学をしていただきました。
健全な人工林へと整備を進めるとともに、間伐した木を販売することで山林所有者様への利益還元に努めています。
今回はハーベスタと呼ばれる高性能林業機械による伐倒・造材や、スイングヤーダによる集材の様子についてご紹介しました。
作業者がより安全にかつ効率的に林業を行うための手法について学んでいただきました。
 ハーベスタの紹介
ハーベスタの紹介
林業現場体験
間伐の一部作業について、参加者の皆様にも体験をしていただきました。
機械作業が導入された昨今であっても、もちろん人による作業は数多くあります。
人による作業と機械による作業の違いを体験し、効率や安全面など木を搬出するまでのリアルについて感じてもらいました。
 伐倒体験
伐倒体験
 架線集材体験
架線集材体験
林業以外の体験を含め5日間かけて体験会が終了しました。
林業に関連した体験をされたことのある方、林業を始めたい方、林業について学びを深めたい方など様々な方にご参加をいただきました。
林業は就業者の平均年齢が高く、また地方特有の仕事です。
今回の経験が少しでも参加者様の学びに繋がり、地方に目を向けること、地域を守ること、そして林業への関心を深めることへの第一歩を踏み出していただけることを期待します。
ツバメの成長と巣立ち
昨年に引き続き組合事務所の軒下でツバメが4羽生まれました。
5月の終わりごろから巣を作り始め、6月の終わりごろに誕生しました。
雛の元気な声に応えるため、親鳥は忙しなく出入りしていました。


産毛が生えている内は幼く感じていましたが、毛が生え変わるとドンドンと大人の姿に近づいていき、雛の姿が見えるようになってから2週間も経つと、立派な大人の姿に。

そして7月の3連休を終えると、4羽とも巣立ったようで、賑やかな鳴声も静かになってしまいました。
代わりに団体客が時折訪れるようになり、今は軽やかな鳴声が聞こえます。

初夏の風物詩も終わり夏本番を迎えました。
暑さに負けないよう体調管理に気を付けていきたいところです。
地域SDGs活動プラットフォーム①
京丹波町で新たに始まりました地域内外協働活動「京丹波町地域SDGs活動プラットフォーム」に当組合も参画し、3/30(土)にイベントを開催しました。(プラットフォームの詳細についてはこちらをご覧ください)
今回は森林資源活用の一環として、ドングリの苗木作り&しいたけの菌打ち体験を実施しました。当日の様子についてご紹介していきます。
ドングリの苗木作り
今回はクヌギのドングリをご用意し、0から育てていただくこととしました。ポットに砂利・土を敷き、その上にドングリを横向けに2つ並べて軽く土を被せます。最後に落ち葉を細かくちぎって被せたら完成です。これからどんどん暖かくなってきますので、2週間もすれば芽が成長してくるでしょう。1年後に苗木として町有林へ植えることを目標に、お世話を頑張ってもらいたいです。


しいたけの菌打ち
続いてしいたけの菌打ちに挑戦していただきました。クヌギやナラなどの広葉樹利用として、当組合では薪やしいたけのほだ木として活用しています。しいたけは特にクヌギ・ナラなどドングリの木を好むため、立派なしいたけが育ちます。
まずは簡単に菌打ちの説明を行い、早速挑戦してもらいました。穴開けはドリルを使用しますので皆さん最初は少し控えめに取り組まれていましたが、要領が分かればどんどんスムーズに作業が進んでいきました。
穴を開けた次は菌の打ち込みです。今回は駒菌を使用し金槌でトントンと打ち込んでもらいました。ドリルは少々危険ですが金槌であれば簡単ですので、小さなお子さんにも手伝ってもらい綺麗に菌打ちを完了させることができました。収穫までには2年かかりますが、枯れないよう手入れを頑張ってもらいます。



今回は春直前の作業として広葉樹にフィーチャーした取り組みに挑戦していただきました。今後は他の季節にも季節の林業を体験していただける機会を設ける予定としていますので、皆様のご参加をお待ちしております。
第69回通常総代会を開催いたしました
令和6年3月2日(土)午後1時30分より、和知ふれあいセンター1階アリーナにおいて第69回 京丹波森林組合通常総代会が多くのご来賓の皆様と本人出席79名、代理出席5名、書面出席82名の計166名の総代の皆様にご出席いただき、開催することが出来ました。
議長には、瑞穂地区橋爪の岩岡始様が選出され、総代の皆様には第1号議案から第9号議案について慎重にご審議いただき、すべての議案が原案通り承認されました。


第1号議案
令和5年度 事業報告、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案、注記表及び附属明細書承認について
第2号議案
令和6年度 事業計画書承認について
第3号議案
令和6年度 取扱手数料、証明手数料徴収額及び徴収率決定について
第4号議案
令和6年度 借入金最高限度額決定について
最高限度額 8,000万円以内 但し、制度資金を除く
第5号議案
余裕金預入先金融機関決定について
京都農業協同組合、京都銀行、京都北都信用金庫
第6号議案
令和6年度 理事14名の報酬額決定について
一金 950万円以内
第7号議案
令和6年度 監事3名の報酬額決定について
一金 50万円以内
第8号議案
一組合員に対する貸付金額の最高限度額決定について
一組合員に対し払込み出資金の20倍以内で200万円以内とする
第9号議案
定款の一部変更について


新年のごあいさつ
令和6年能登半島地震によりお亡くなりになられた方々にお悔やみ申し上げますとともに、被災されました皆様に心よりお見舞い申し上げます。被災地の1日も早い復興そして被災されました皆様の生活が早く平穏に復することを心よりお祈り申し上げます。
皆様におかれましては、ご家族お揃いでご健勝にて新年をお迎えのことと心からお慶び申し上げます。
旧年中は、森林組合の事業推進におきまして、各行政区の林業推進委員様をはじめ、総代の皆様に、格別のご支援ご協力を賜りましたこと、厚くお礼申し上げます。
本年も変わらぬご厚情を賜りますようお願い申し上げます。
さて昨年を振り返りますと5月8日には、新型コロナウイルス感染症の位置づけが、「5類感染症」に移行され、日毎に通常の生活が戻って来たものの、ロシアのウクライナ侵攻による争い、またパレスチナとイスラエルによる戦争と多くの犠牲者が出ている中、この争いによる影響は、わが国をはじめ世界各国で物価の高騰等、大きな影響を受けているところであります。
一方、地球温暖化による影響と思われる大規模な森林火災の発生や、集中的な豪雨が世界各国で発生しており、7・8月には九州地方や東北地方でも記録的な大雨による土砂崩れ等大きな災害が発生しました。
また昨年7月の世界の平均気温も観測史上最高気温を記録し、国連事務総長が「地球温暖化時代は終わり、地球沸騰化の時代が到来した」と発言もされました。これまでの気候変動における対策をより加速させる必要も示され、昨年12月13日に閉幕したCOP28においては、「化石燃料からの脱却を進め、今後10年間で行動を加速させる」と定められました。
こうした情勢の中、森林組合の運営におきましても、地球温暖化防止や災害防止を目的とし、森林整備を進めるために必要となる地方財源を安定的に確保する観点から、令和元年度に「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。
既に「森林環境譲与税」は、国から各市町村への譲与が開始されており、京丹波町も当組合と連携し、町内の未整備森林を対象に森林境界の明確化を進め、「森林経営管理制度」において森林整備を図り、森林の持つ機能が最大に活かされるよう取り組みを進めているところであります。
また、「森林環境税」は、令和6年度より各市町村において、個人住民税均割と併せて、1人年額1,000円の徴収が行われ、年間に総額で約600億円となり、この全額が先程の「森林環境譲与税」として、各市町村等へ譲与され森林整備等にと活用されます。
特に令和5年度は、次年度からの各市町村へ譲与される「森林環境譲与税」の配分額の見直しの年であり、京丹波町からも畠中町長様をはじめ京丹波町議会より国へ要望書並び意見書を提出いただきました。
こうした取り組みにより、令和6年度からの「森林環境譲与税」の譲与額が、山間部の各市町村には今までより手厚くされることになりました。
本当にご協力いただきました関係者の皆様にお礼を申し上げます。
また、3年目となりました京丹波町より委託され取り組みを行っている森林環境教育も、令和5年度は丹波ひかり小学校と瑞穂小学校の児童の皆様を対象に、森林に入り直接立木に触れ、また林内の表土を観察する等、森林の働きや木の大切さを学んでいます。
そして森林の中で働く職人達の仕事を学び知るため、杉・桧を伐採し高性能林業機械により造材する現場での作業の様子と、直接職人達から話も聞かせてもらっています。こうして子供のころから森林の持つ機能と共に林業という職業を知り学ぶ機会を持つことは、本当に大切なことであります。
こうした事業を京丹波町から委託を受け、そして組合員の皆様が所有されている森林においては「森林経営計画」を樹立し、町より認定も受け組合へ委託いただき搬出間伐並び新たな作業道の開設と、隣接する広葉林においては優良な広葉樹の育成の施業等、総代会でご承認を受けました令和5年度事業をほぼ計画通り進め、昨年12月末を持ち当森林組合の令和5年度事業を締めくくることができました。
関係機関をはじめ、京丹波町の皆様には格別ご理解ご協力をいただきましたこと厚くお礼申し上げ、本年におきましても役職員一丸となり事業の推進に努めてまいりますので、引き続きご指導ご支援をお願い申し上げますとともに、皆様方のご健康ご多幸を祈念し、年頭のごあいさつといたします。
京丹波森林組合
代表理事組合長 樋口 義昭
林大祭へ出展しました
12月3日(日)に京都府立林業大学校で開催されました第8回林大祭へ当組合も出展しました。今回ご用意したのが、杉・桧を使用した『木のたまご作り』です。卵型に荒削りした原型を紙やすりで磨き、杉の葉・ヒカゲノカズラでデコレーションして完成です。
当日の様子を少しご紹介します。

今回ご用意した木のたまごの原型。白い方が桧・濃い方が杉です。

丸く、凹凸が滑らかになるようにやすり掛けしていきます。

用意した植物と竹籠を使ってデコレーションしていきます。

完成!

下は2歳、上は73歳まで総勢52名の方が体験してくださいました。
初めての取り組みということで模索しながらのご提供となってしまいましたが、皆さんに満足してお持ち帰りいただくことができました。ご参加くださいました皆様ありがとうございました。
木に親しんでいただける木育体験を様々な方法でこれからもご提供できるよう挑戦していきますので、機会がありましたら是非体験してみてください。
令和5年度 森林組合感謝DAYを開催しました
組合員様からの開催要望の声もあり、令和5年12月2日(土)森林組合瑞穂支所(橋爪)、3日(日)森林組合和知支所(本庄)にて「森林組合感謝DAY」を開催しました。
チェーンソー等の機械器具の無料点検及び整備(目立て等)の実施や椎茸原木、のりあみ等の展示販売を行いました。風が冷たく肌寒い2日間ではありましたが、111名の方にご来場頂きました。
また、ヤギさんも来られ、チェーンソーを購入したいようでした!(笑)




令和5年度 京丹波森林組合コンプライアンス研修会開催
令和5年10月20日に農林中央金庫 大阪支店 業務第二部より講師にお世話になり、午前は役職員を対象に「役員の役割及びハラスメントを防ぐ態勢について」学び、「ハラスメント対策は『初期対応力』で決まる~リーダー・管理職・経営層に必須の初期対応力~」のDVDを鑑賞し、健全な企業経営を行うために求められる企業体制の構築や企業の内部統治の徹底さを学びました。


また、午後はFK(現場作業員)並びに職員を対象に「ハラスメント事例とハラスメントを発生させない心構えについて」を学び、「ハラスメント対策は『初期対応力』で決まる~被害にあわない対応法、会った時の相談方法~」のDVDを鑑賞し、ハラスメント防止に向けた心構えとして、よりよい人間関係づくり、良好なコミュニケーションは日頃の積み重ねから、しっかり・はっきり・気持ちよくあいさつし、感謝の気持ちを伝えることを忘れないことが大切であることを学びました。


改めて一人一人が、お互いを認め合い、風通しの良い職場づくりに取り組む意識を再確認できました。
また、同日にFK(現場作業員)並びに職員を対象に人権研修会(DVD鑑賞)を開催しました。お互いが支え合い、温かく見守りあう地域社会の大切さを学びました。
令和5年度 林業推進委員会議を開催しました
今年も「林業推進委員会議」を開催しました。9月21日(木)に、わち林業センターを会場として、9月22日(金)には、京丹波町役場防災会議室で行い、合わせて49名の林業推進委員様にご出席頂きました。
今年の会議では、以下の内容について説明を行いました。
・森林経営計画に基づく間伐事業の推進について
・保安林指定森林における森林整備について
・森林環境譲与税関係事業について
・インボイス制度について
特に「森林環境譲与税関係事業について」は、平成31年4月からスタートした森林経営管理制度について説明を行い、森林環境譲与税を充てた事業として、町から委託を受け「森林経営管理意向調査」及び「山林境界明確化」の進め方についてお伝えしました。
また、「インボイス制度について」は、令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)が導入されます。消費税及び課税事業者・免税事業者の違いや間伐を行った木材を搬出した際に、当組合を通じて木材市場等に販売し、お預かりした売上代金の精算方法等をお伝えいたしました。
森林組合と森林所有者皆様とのパイプ役をお務めいただく林業推進委員様には、ご多忙の中、何かとお世話になりますが、よろしくお願い致します。


リスクアセスメント講習会開催
林業における労働災害の発生は、減少傾向にありますが、災害の発生度合を表す「年千人率」で他産業に比べると全産業の中で最も高くなっています。
年千人率とは、1年間の労働者1,000人当たりに発生した死傷者数の割合を示すものである。
令和4年の「年千人率」では、全産業平均が 2.3に対して林業は、23.5と約10倍の発生率となっています。また、令和4年の林業における年齢別死亡災害発生状況では、50歳以上が57%を占めており、作業種別の死亡災害では、伐木作業中の災害が63%を占めています。
令和5年9月8日に労働災害を防止するため、災害発生の原因となるものを取り除くことが必要であり、林業・木材製造業労働防止協会京都府支部 藤井 文夫 氏 及び 技能師範 古屋 昭 氏 から京丹波森林組合 FK(現場作業員)と職員を対象に、林業労働災害の防止及び令和4年林業労働災害について学び、リスクアセスメントの指導を受けました。

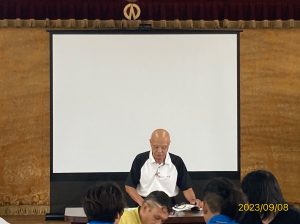
各班に簡易リスクアセスメント実施事例のイラストを見ながら、どのような作業でどのような災害を受けるのか、「危険の洗い出し」を「~するとき、~したので、~(事故の型)になる」の3段階で災害に至る過程を明らかにしました。また、「災害の可能性・重大性」のランク評価(1~5段階評価で、数字が高ければリスクが高い)についての意見も出し合い、どのような「低減対策」が必要なのか話し合いました。


この指導を基に、当日作業のリスクアセスメントを行い、ゼロ災害を目指して安心・安全な山づくりに努めています。